
敵対種族の領域に関する調査報告書
リミエ・カトリイ一刀長 様

調査結果につき、以下の通り報告します。
なお詳細は下記ファイル転送済みですので、申し添えます。

1:サンプル「ニーナ・ウィナス」の居住惑星について。
星系の位置、惑星情報についてはファイルの通りですが一部補足します。
公転軌道は地球に比べて緩やかで、このことは下記妖精と呼ばれる生き物の社会形態に影響を与えているものとおもわれます。
御使い達は彼らのことを「妖精達」、その世界を 「下界」と呼んでいますが、ご存じのとおり、ここ数十年の調査や言語解析、及びその意図的な情報流出による報道により、わが第8管区の付近住民達にも敵対 種族は人工惑星に住む「使徒」とそのしもべである者の住む俗称「妖精の星」があると知られているのは承知のとおりです。
人口は私の調査した見た範囲が安全上の理由から限られていた為、惑星全体の数値はわかりませんが、我々の尺度で15年程前の妖精達の世界の資料によれば、およそ人間(つまり私たちの言う妖精)が2億8千万人、御使いの常駐数が平均4万人程度と記されています。
大きさはおおよそ我々の8分の1、(20〜24cm)程度、知能や感情を含む精神年齢は私たちの7歳〜13歳程度に相当します。
この大きさが先天的なものか、御使い達が操作しものかは、今後の更なる科学調査を待たないといけませんが、いずれにせよ、おそらくこの大きさが最低限の知能を維持して、亜人類として社会を維持出来る大きさの限界かと推測されます。
なお、本サンプルは、御使い達の降り立つ地に近い 海岸沿いの町規模の地、彼らが「ロラン」と呼ぶ地の近くにて採取しましたが、この地域の「妖精」には「防壁」に関わる特殊な能力を持つものを集めていると の情報があり、私見ですが、今次の作戦の課題である新型の彼らの「防護壁」の突破にもつながる情報が隠されているものと期待します。
なお、彼らの独特の風習と習慣、お迎えと呼ばれる御使いの人工惑星へ召還される儀式についてはまた項を改めて報告したいと思います。
2:御使いと呼ばれる我々と同サイズの異星人達の住む人工惑星
大きさは我々の月より2割増し程度、少なくとも惑星全体が規則正しい配列によってなっており、彼らの惑星の上空46万kmを遊星として廻っています。
外表大気はなく、建物は全て空洞内部にあり、少なくとも数箇所以上の「魂」交換房、再生施設、冷凍保存室、遺伝子情報室が配置されています。
また、御使いたちの居住区、防衛網は全てこの区画と切り離されて建造されていて、それぞれの色区分で階級分けされた特定の者のみが施設に立ち入ることを許される構造になっています。
防衛網もまた独特で、「ミタンニの矢」と呼ばれる追撃隊があり、私もこれにより帰還直前に追われました。
構成は通称我々が俗称「サファイアカット」とする無尽追跡機と、下級御使の搭乗する指揮船からなっています。
彼らの領域から脱出するにせよ、進入するにせよ、2重の防護網、防護壁を突破しないといけません。
この解除認証は自動で行われますが、通常は部分解除にとどまり、全面解除は緊急時の特定コードを持つものしか行えません。
御使い達は彼らの領域を統治する神々と呼ばれる生き物の1人「留守を護る者」のそれぞれの「試練」と飛ばれる審査により階級分けされ、役割が与えられているようです。
続きは次回のレポートにて

日 誌 (統合作戦本部提出戦略リポート草案を兼ねる)
紀元2632年6月11日
リミエ・
カトリィ一刀長/防空宇宙軍調査部少佐
この時代、人の精神を他の人間の肉体に移し替えることが可能になった。
これは、本来敵対種族であとどまってる御使い達の技術だったが、この頃までにはその装置「交換房」そのものを奪取し、
研究することで、人類側においても可能となったものである。
ただし、以下の要件が必要な上、理論的には意識を自己より若い他者に移すことで、不老不死となることから、
倫理学的問題もあって人類側では一般化していない。
1:あらかじめ必要因子を胎生時に組み込んでおくこと。
2:出来る限り、他者の意識が混在しない環境に装置を設置すること。
3:互いに適合可能なこと、可能な限り遺伝特性が類似していることが望ましい。
この内、
1の条件については、未だ解明されていない為、方法としては「試練」から逃亡し、人類側に亡命した御使いとの種族融合計画の副産物である混血以外に解決策がない。
2の条件については装置は可能な限り混在を避ける為、へき地の山頂や、宇宙空間上にプラントとして配置されている。
3については、本来元体の複製(クローン)に転移
交換させるのが最良であるが、民需では敵対種族の因子を入手できず技術的な限界がありこと、「転移倫理法」の問題もあって合法的には行われておらず、非合
法ルート良質のサンプル入手は軍の違法横流しに頼る他ないため、成功例はごく少ないようである。よって我が防空宇宙軍第8管区においても、このような転移
は、現実の使用目的からみても、少数の実験を除いてほとんど行われていない。
一方、敵対種族(御使い側)では事実上全ての構成員に上記因子が組み込まれている。
「御使い達」は、「留守を護る者」と呼ばれる上位者から、「試練」と呼ばれるテストを経過して様々なクラスに分けられている。
これまでにも御使い達の住む人工惑星と(俗称)妖精の星とが単なる主従以外にも何らかの関係があるのではと、学者の間で言われてきたが、今回の潜入調査で、新たに次のことが判明した。
1:妖精(俗称)は御使いの幼生体である。
2:妖精は、一定の期間が経過、我々の基準で言う「思春期」前期の成長段階(これはおおよその基準で、これより早いものもいる)
に達すると、「お迎え」と呼ばれる儀式により、御使い達の航宙船により、人工惑星へと運ばれる。
3:移送先で何らかの基準で選抜を行い、合格したものだけが、意識をあらかじめ用意された我々と同じサイズの身体に移され、元の肉体は処分される。
4:選抜に失敗したものはその妖精の姿のまま、僕(しもべ)として残り数年の寿命を迎えるまで御使いに奉仕する。
5:上記儀式の歳に与えられる成長剤はその名の通りの効き目はなく(偽薬)、後で行われる3ないし4の過程のようい記憶抹消手続きに必要な触媒に過ぎない。
6:選抜に漏れたもの「幼生体」の中には御使いの愛玩目的の為、何らかの処置を受けるものもある。
いづれにせよ、我々は彼等の技術を奪取することにより、工作員を送ることが可能になった。
現在、特別な資質を持つ工作員を投入してもなお、潜入工作はその性質上、防備を厚く出来ない妖精達の惑星においてのみ成功し、機器奪取も物量を投入できる辺境地(御使い達にとって)の交換房設置衛星に留まっている。
防壁(シールド)の問題について。
今後の作戦の課題は、敵対種族の星系の本拠地に攻撃を可能とすることにある。
宇宙開拓時代の黄金期に資源豊かでかつ人類の居住可能な惑星を発見しながら、異種生命体の介入により、むざむざとこれを放棄しなければならなかった祖先の苦渋は察して余りある。
とはいえ、40光年余りというのは空間航法が可能となった現在でも、決して費用対効果が引き合うものではなく、最小の犠牲で最大の効果が引き出せるようになるまで、大規模な作戦は控えるべきである。
防壁の構造について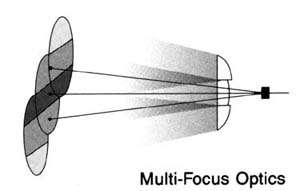
敵対種族が展開する防壁には大きく分けて3種類がある。
<物理型>
・実体弾、荷電粒子、ビーム、物理的な衝撃を跳ね返したり吸収してしまう種類のもの。
<遮断型>
・ 紫外線や宇宙放射線を遮断するもの(自衛用と言うよりは生活安全の為のものである)
<精神障壁型>
・ 知的生命体に作用し、精神的苦痛を与えたり、それに付随する電磁波などで、頭痛等の障害を引き起こし、心理的に侵入を拒ませるもの。
これらの障壁は常に展開しているものではなく、必要に応じて展開したり、強弱を状況に応じて変更しているようである。
御使達の本拠地である人工惑星はもちろん、各拠点には強力な防護壁があり、防空宇宙軍の長距離砲艦の有効射程内に入ることもできないため、又強力なジャミングもあり、困難な作業ではあるが、彼らの内部に内通者を作らない限り、突撃部隊を送り込むことも実現出来ない。
しかし、一方で、歩兵レベルでの敵対種族の肉体的 能力はは本格的な軍隊組織もないことから脆弱で、防衛担当の御使いも我が方の相当する厳格な戦闘訓練を受けていない為、彼等の統率者の能力が不明の為、危 険は残るものの、障壁を突破かつ無効にして内部に兵を送り込めたなら、容易に制圧は可能とおもわれる。
いずれの障壁もそれ自体、独自のノイズを発生して障壁内部の者に長期的に見れば影響を与える危険性がある為、遮断型以外の障壁は常時接続しているわけではない。
特に妖精達の環境(天然惑星である)と交換房付近は上記問題の影響をさける為遮断型以外の防壁を極力使わないのが彼等の方針らしく、このことが作戦の成功率の多寡に影響している。
無人転送爆弾内蔵の機動兵器(俗称甲冑魚)対策について。
従来敵対種族との交戦は局地戦に留まり、我が方の艦隊(又は船団)が太陽系外に出ない限り、彼等が干渉及び攻してくることはなかった。
しかしながら、ここ30年の間にがその方針に少しの変化があり、軍事基地が空間転移技術を応用した機動兵器の急襲を受けるようになった。
原因としてはサンプル数の採取の増加や情報の漏洩に彼等が危機感を抱いたことが推測される。
彼等独特の思考形態なのか、それとも彼等に「人道的」などという概念があるのかは不明だが、民間地域への無差別攻撃はまだない。
大気圏、重力圏の高密度条件で空間航法を絶対精度で行う技術は残念ながら未だ我が方では開発途上である。
対策としては、
1:防諜を強化して重要な基地は人類同士の交戦時のセオリー同様に電子的、視覚的に偽装の上、地下基地化すること。
2:、絶対座標の算出の基礎となる偵察機の早期発見と撃墜。
3:さらには転移前の発出空間の出現そのものを阻害する、自動関知式の複合発信電磁波、衝撃波発生装置の標準装備。
4:最終防衛手段として奇襲の対策訓練をした即応部隊による基地内部での機動兵器殲滅。
によりほとんど防止できるものと力説する。
なお、高速の移動手段を持たない甲冑魚タイプ(外 見上そう俗称される)の機動兵器は、鈍重な為に捕捉は容易なものの、当初より自動爆弾としての使用を主に設計されており、核兵器相当の爆弾を内蔵し、我が 方の物理障壁ではくい止められず、装甲も強固なため、万が一転送を許すと対応できない。
細心の注意が必要とされる。 (結)
「ゆりかごの巨人」 前章
1 前 哨
星のかけらが漂っている。 それは慣性と外惑星の引力の作用によって漂い続けていた。
「地球では東部日時で12月24日を迎えたばかりのころだ」
航法士がぼやくように呟く先に一時間前に遮光スモ−クを解除した船窓がある。
彼は太陽風も届かない外惑星軌道から、二人の息子と一人の娘に前もってプレゼントの内容を聞いておくべきだったと後悔しているのだった。
太陽系の中心部の輝きは、まだかろうじてぼんやりと燐光のよう長い尾の残像を引いている。
航宙担当がまだ緊張が解けない動作で「ささやき」艇長を起こしにかかった。
「一刀長?今は船乗りだから艦長で構わないわ」
ーもっとも移乗したこの船の規模は艇長と呼ぶべきねー
「起きていらしたと・・・失礼しました」
「監視員と二羽の妖精を起こしてあげて」
この船はただ一つの目的のために偽装されていたので、あらゆる外部推進機関と無関係でいる必要があった。そのためにこれからただ1回のジャンプで御使いの領域すれすれに到達しなければならない。
トゥ−ルは“ヘカリィ”に問いかけられた。
「りゅ−い、わたし、もうへかりぃじゃなくてもいいんでしょ。だってもう巨人さん、帰してくれるって言ってたもの」
「そうだね、あり−あよく頑張ったね。」
コ−ドネ−ム“トゥ−ル”は七歳の“ヘカリィ”とあまり変わらない年齢だったが、よく訓練されていて、彼女を心配させるようなことのないようにと話しかけたりしていた。
「トゥ−ル、時間よ。準備させて」
彼等の監督者はヘカリィの寿命の三倍以上もの時を生きていた。 ヘカリィはトゥ−ルが彼女を何と呼んでいるかを聞いている。
しかし彼女が初めて巨人を見た時に恐怖のあまりどのような反応を示したかを忘れてはいない。
それは以前の彼がそうであったように。
彼等が初めて会った「巨人」の名はマ−ルと言った。
目標地点前でトゥ−ルは心配になった。
「本当に帰していいんだね、義姉さん?」
「話したとおりよ。あの仔を御使いの船に乗せるまではあなたの仕事。それが終わったら、この場所で待ち合わせ。時間まで来ては駄目。」
「見つかってしまうからでしょ、義姉さん」
「私の正体が知れたと思ったら迷わず艇を呼びなさい、それができたら・・・」
彼が何かと尋ねたので、マ−ルは出かかった言葉を打ち消すために別の結びを続けた。
「あの仔は戻れるわ」
「そうだね、よかった。そのままなんて、なんとなくいやだったんだ、でも、あのコ、帰すの本当って聞いてなんだか・・・安心した。それに、このおつとめもこれで終わりで・・・そのせいもあるかもしれないけど・・・なんだか・・・」
「君もよく頑張ったわね。でも本当は帰りたいんじゃないの?」
「ぼくはもう・・・遅いから・・・いいんだ。みんなに知られているし」
“小惑星のかけら”は直ちにゆりかごを乗せた船を占拠した。
この時期の船が積荷である仔に悪影響を与えないように極力化してあることは以前の調査でわかっていた。
調査結果の通りなら御使いの疑似パタ−ンを持つ彼と登録済みの仔であるヘカリィの造り出す解除コ−ドにより膜に拒絶されることなく神々の領域に侵入できるはずだ。
作戦名は人類に火をもたらした者の名を取り「プロメテウス」と呼ばれ、この特殊艇も同じ名で呼ばれた。
それはヘカリィ、つまり彼女を地上へ向かう舟、「ゆりかご」に封入させることで終了することになっていた。
あまりに親切すぎるかのような行動だが、真意は別のところにあった。
ただ、トゥ−ルはそれが実験を兼ねているのだと、もし失敗した時は再び連れ帰るのだという説得に納得したのだった。
たとえ彼が数年もしないうちに自分が「偽善」を行っていると気づくことがあるとしても、今の彼にはそれが全ての安堵の理由だった。なぜなら彼は巨人達の世界にいながらもずっと隔離されていたのでこの説明に疑いを抱くことはありえなかった。
「事情が変わったわ。予定を変更、トゥ−ル。その仔は私が連れて行きます。君は先に戻って待ってなさい。港に行くには御使いのいる所を通り抜けないといけないの。私とこの仔なら怪しまれない。あの場所なら艇が来てくれるわ」
「義姉さんは?」
「後で追う」
「わかった。必ず戻ってよ。ちゃんと待ってるから」
ー しかし ー
艇は迎えに来なかったし、マ−ルが戻って来ることもなかった。
それから間もなくの内に御使い達は滅菌処置用の予備加熱室の始動しようとして衰弱した未登録の仔を見つけ、以前連れ去られた仔の魂が損傷した巨人の雌の抜け殻に宿っているのを聖域の近くの交換房で見つけた。
2 幼年期
(ヘカリイの巨人達に対する体験の記述より)
「ここでは人は7才で大人になり、およそ14歳で一生を終えるのです」
「ある異生体は、その澄んだ声がにごり始め、同生体でさえ、豊かな髪はそのままに、老いが異毛症を、脇の下や陰部、男では鼻や顎下にまで転移させると、嘆く間も無いうちに「御使い」が天から『お迎え』に来るのです」

「こ
のあいだが卒業式だった。ああ夏も終わるなんて考えている間に卒業生代表の黄色のハパネラ君と緑銅のウルスラさんが式辞を読み終えてしまって、ぼくはきっ
ぱりと学校の野庭の赤く染まった葉っぱを見上げながらそそくさと、でもちょっとひきずった感傷に彩られて仔共(こども)の日々におさらばした。
半年の後にぼくは七才になる。でも成人祭までなにもしないというのは、僕たちにとってとっても、すごくもったいないことだった。昼食の飲み物を持ってきてくれる銀黒のカルムおじいさあんはよくこういってるね。
「君たち、何もしないでいるとすぐに“お迎え”が来てしまう。だからどんなわずかな一時でも大事に思えるようにしたいね」
このおじいさあんはとっても元気な人で、普段は校庭の手入れをしているけど、僕たちと学級新聞を造るのが好きで、時々ひょいと木に登ってそこから見える
景色をスケッチしたりする。昨日はそのカルムさんから西の川岸公園を描いた一枚をお祝いに貰おうとしてひどいめにあってしまった。調子に乗ってもう一枚貰
おうとしたらさっき話したウルスラさんが僕を抱えていきなり駆け出したので僕はもうただびっくりしてしまってすごく恥ずかしかった。何を考えているんだろ
う?
大人になる頃になるとどうして女の子、じゃなかった女性の方が背が大きくなるのだろう。昔何度か母さん父さんとに聞いてみたけど。たしかなことは聞けな
かった。でもそれはどっちだっていいことだと、そうするべきなのだと最近ようやく気が付いた。幾何学の時間に三角形の長さと比率の仕組みのわけを知るよ
り、それを使って出来る形の不思議の方がずっと「なぜ?」な気持ちがする。でもきっとそんなものなのだろうか?

2
「僕は学校を卒業して就職するまでの間、マ−ルさんという考古学者の発掘の手伝いをすることにした。天寿を全うするような歳になってもこんなことに興味を
持つなんて学者って人は彼女に限らずよほど変わった人だなと思っている。ところで今僕らが掘り返しているのが『禁じられた場所』だってことは最近知った。
遥か昔に僕達の2倍ほどもある巨人がこの地球に住んでいたという話は子供の頃何度も聞かされた。神話なんかではいつもこんな風に書いてある。
“ 巨人達は人をそそのかし、悪しき種を植えつけて天に反抗させようとしたので、神は御使いを遣わしてそれを滅ぼされた ”
・・・年代記第12章より

一度はアルバイトを辞めようかとも思ったけれどまだ言えずにいる理由。それってのがマ−ルさんのまるで好きな人に熱でもあげるかのような話し振りが、それこそ遠い昔のように思える退屈な学校の先生の呪文とは違っていて一日が短すぎるせいだ。
最近、もしかしたらずっと昔には“お迎え”の先があって、神話の世界の巨人達もまだどこか遠い所で生きているかもしれないって気がしてくる。でもこんな
事を話したら僕は病院に入れられてしまうだろう。それにマ−ルさんには堅く口止めされている。もちろん僕もそうするつもりだけど」
3
「おはよう、ニ−ナ君」
「おはよう、マ−ルさん」
このあいさつのとき僕はすぐに「−」の入ったところがこだましていることに気づいただから時々二回くり返してみたこともある。「大人気」ないなとわかっているいけどハミングは楽しいんだ。
「今日は“一ニ歳の場所”を掘るから」
この人は本当におもしろい人だと思う。マ−ルさんのは老人向けのリュックなので大きくて重く、僕たちのような仔共を終わったばかりの体にはずしりと感じ
る。だから僕はお願いして僕に合った大きさのリュックをお店に行って一緒に作った。今回のお代わりは火曜日のお手伝いじゃなくていらなくなった僕の前の服
との交換にしたよ。
一ニ歳の場所っていうのは僕たちの秘密の合い言葉だ。数が増える程不思議が増えるし、地層が古くなるから。
でも少し怖い気もする。だって・・・じゃなかった。なぜなら もう少しであのお迎えの年にいきついてしまうから。

汗が出る。これはいやなんだ。だって僕の中の試練が増えるから。ヒュ−イ君が僕は試練が足りないっていってた。でも僕はこんな時つい行き過ぎてはしゃいだり、あせったりしてしまう。マ−ルさんはどう思うのだろう。
「あの・・・」
「ロ−プ、絡まないように注意してて、先に降りるから。」
聞きそびれて、あれ、まだ言ってないんだから「話しそびれて」かな?言い方変だね。
風は無かった。ニ−ナは汗をちょっとずつタオルで拭っていた。あともう少し待てば午後の風の時間だ。すぐに涼しくなる・・・
誰?マ−ルさんが呼んでいる。でも上に誰かいないと何かあった時に危ないからって、だから僕が手伝いでいるんじゃなかった?
「大丈夫、そこに予備のロ−プがあるでしょう!」
僕はそれを見つけたので返事をした。
「それを降ろして、それからね・・・」
僕にはそれはとても重かった。マ−ルさんみたいにもっと年をとれば簡単に持ち上がることはわかってる、でもそれができるってことは、僕はあのとうもろこ
し草のある僕の家にいられなくなることなんだ。だから力を持つことは本当はとても怖くて寂しいことなんだってお母さんは言ってた。
「だって彼や君と一緒にいられなくなるでしょ、それならお迎えなんかこなくてもいいわ。お母さんはそう思っているの」
今日もそうだけどマ−ルさんはロ−プ一本につかまって降りて行ってしまった。すごい!けどぼくにはまだ出来ないんだ。このどうぐ、だからなんだと思う。
マ−ルさんの三りんの両脇の荷物入れから四つ、二回にわけてその急斜面まで、先のほうが霧みたいな感じでよく見えないその場所まで運んだ。ここは僕たち
のルワ−スと違ってとてもあつういんだ。だけどその下の感じはなんだか涼しそうに見えた。手の汗で金具が滑る感じがする。両端を二本になったロ−プに引っ
かけて取っ手を開くとそれは
「しゅ−っ」
と下に向かって走っていった。
「かちゃんっ」
残りは僕のだよね、マ−ルさん。
それで早く降りようとリュックのひもを締め直していたら、さっき降ろしたどうぐ、手袋と肌が見えた。
「駄目よ。手を拭いてからじゃないと」
手には汗がいっぱいだった。
「滑るといけないから、はいこれ」
ちょっとひんやりとした手の感じ。楓の香りのする白いパウダ−が僕の手を白くして、指のすきまに白まりもを残した。
そしてマ−ルさんはまた先に降りてしまった。僕は足を乗せる、かちゃっという音と一緒にそれは僕のつま先を留めた。そして手で上の金具を握るまでのあの怖い感じがやってきた。
「かちっかちっかちっ」
よし、上の金具を握ったよ。僕はちょっと息を吸って、ゆっくり吐いた。そして足をちょっと開いたし、手の金具の取っ手をちょっとひねった。
「す−−−−−−−−−−−−−−」
空がゆっくりと小さくなっていく。なんだか静かになっていくみたいだ。静かさってひんやりすることなんだろうか?風じゃないけどなんか流れみたいのが僕
の下だけだったのが横や上からもくるようになったころ、マ−ルさんが僕を待っていたのがわかった。そう、上の世界は暑くて砂が吹いていやなところ、試練の
ところ。
でも僕たちはここに来ていて、僕はちょっとどきどきしている。どうしてここはこんなに不思議なんだろう。蒸し過ぎた棒ぷれっとのようにくるくると曲がっ
た岩の建物。すごく天が遠くにあって、巨人さんたちってよっぽど大きかったんだなとちょっとまた怖くなった。でもちょっとさっきとは違う感じ。
「マ−ルさん、ま−るさん、これがそうなんだね。すごく大きいね。でもどうしてこんな変なかたちをしているんだろう?」
「溶けたのよ。ずっと昔は岩が溶ける、そんな不思議なことがあったはずよ、たぶん」
「ここに住んでいた人・・・巨人さんたちはどこへ行ってしまったの?」
「今はいないわ。でも近い人たちがどこか遠いところにいるかも。そこでは私たちと巨人さんたちが一緒に暮らしている、そんな世界があるかもしれないわね」
「それってきっとよい巨人さんなんだね。だってそうでなければここの巨人さんみたいに神様が罰するはずだもの」
「え、ええ、たぶん」
ほんとうに不思議な人、マ−ルさんってずっと昔のことなのに、どうしてこんなにいっぱい知っているのだろう。あ、これ・・・なんだろう?
「きれいなガラス、うすい青、ちょっと赤の紫、御使い様の舟の光みたい・・・きれいな色、ガラスの中、時の泡が止まっているね。これ持って帰っていい?」
「きっと同じものかも」
「?」
「気にしないで、さあ、もう行きましょ。あまり長くここにいるのはよくないわ。それは持って帰ろうかしら。それ、しっかり封をしてね」
−かちっう、かちっかうかちっう、かちっかうかちっう、かちっかうかか−
僕たちは外に、空が拡がる地面に出た。あいかわらず暑かったけど風が吹いていて、それになんだかさっきより気分がよかった。
マ−ルさんのは“ 三りん ”だから早いんだ。明日には帰れるよ。
お母さん、お父さあんへ
青草月二二日 月三つの夜に
手紙を書き終えて彼はそれを肩からかけている採取ポ−チのポケットのファスナ−を開いて差し込んだ。
この間から一つの話がずっと気になっていた。
−今もどこかで生きているんだって。マ−ルさんは特別だからお迎えの後でその世界に行けるんだって−
お迎えの先がどうなっているのかはよくわからなかった。ただ御使い様の世界があって何人かはそこに入って暮らしているらしいという噂がぼんやりとした幸福を約束していて、そのためか彼らの心配がいくらかほぐれることとなっていた。
−御使い様は言ってた、心配することはないって−
4
今日のお手伝いは結構早く終わった。
「それが本当なんだろうか?確かめるたった一つの方法・・・それはマールさんと同じように〃死ぬことだ。特別な場合に赦される老化剤を使えばお迎えが来る
事は知っていた。もちろん猛反対された。使徒庁にいる父が最終的に僕の側にまわってくれなかったら到底無理だったか もしれない。あの人は言ってた。
「他の生き物はあんなに衰えて死んでしまうのにどうして人間だけにお迎えが来るのかって、考えたことある?」
「でも声がおかしくなったり、病気になったりしますよ」
「それはどうかしら?」
午後の日差しが幾分弱くなっていた。昔の感覚なら15時頃・・・・いや民間人なら后後3時と言うだろう、今日の作業も終わった・・・お茶でも用意してもよい頃だ。
計算ではなく、感覚でこの世界を捉えることをマールは大分以前から訓練してきたのに、換算で考えていたことに気づいてはっとした。
「紫の時2つ、そろそろ今日は終わりにしましょう」
マールはスクーターの方に顔を向けた
僕はスクーターに道具をのっけるために、袋や工具箱をまとめはじめた。
まとまるとけっこう重くて、引きずるようにして運び始まると汗が止まらなそしたらもう1つの袋はマールさんが持ってくれた。
大人って力持ちなんだ。だから僕も早くあんな大きいものが持てるようになりたいって言ったら、
「いいことばかりじゃないのよ、それは」
「そうなんですか?」
「だってそうなるとすぐにお迎えが来るから。そしてその先があったとしても」
「巨人さん達ってそのずっと先まで生きていけるんですよね。御使い様達と同じ位ずっと・・・なんか、すごいね!」
そういうとマールさんはちょっと不機嫌そうな顔をしたような気がした。
四輪スクーターに大きな布袋を載せると、少し傾いたかみたいに音がした。
「ダメでしょ!左右で同じ重さになるように積まないと!」
今日のマールさんは少し様子が変だなって思う。もうすぐ雨の季節だから?作業ができなくなるし
マールは四輪のパネルに手をかざし、認証をすると、ハンドルを握った。
ここまで気づかれずに来れたのか、それともわざと見逃しているのか、彼女には未だにつかめなかった。
ただ、このような場合でも、何人かは確実に任務を成功させている。
この車両にしても全て「天からの授かり物」で、壊れた時でもここの「人間達」は自力では直せないのがもどかしかった。
一応、御使いのいる場所の近くに工房があり、部品交換や簡単な修繕はしていたが、そんなことをしていては露出が多くなり、感知される危険が増すことになる。
だから、マールは送り込まれた器具や工具を使って多少の不具合は自力で修理していた。
間もなく雨季に入るのか、紫よう花が咲き誇っていて、風に花びらと、その髪の毛のようなせん毛を揺らしているのが目に入った。
マールは博物学研究室のある自宅に着いた。
ここは元々前任者が住んでいた場所だった。いや、正しくは彼女本人の姿をした前任者がいたはずの場所だった。
最も疑われるべき職の者と、彼女が入れ替わっているなどとは誰も思いはしない。
これには内通者を養成することができたことが大きかった。
「今日は、少しお話があるから・・・」
道具袋を倉庫にしまい、身体を洗い流し終えた頃には、少し夕暮れがかっていた。彼の方へ飲み物を差し出しながら、彼女はそのように言ったのだっった。>
「本当にそれでいいのね?」
彼はそれにはすっと首を向いてうなづいた。
「だって、向こうで又会えるんだもの。少し早めに往くだけだもの」
今まで何度もそれとなく確かめたはずなのに、彼女はまた同じ問いを繰り返していた。
3 緑青という御使いの誕生
その少し以前、彼らのはるか上空の天体では、残された生き物、トゥールとコードネームで呼ばれたエージェントが目を覚ますとこだった。
トゥール彼、いえ、正確には彼らが目を覚ましたとき、周囲がぼんやりと暗く、身体もどういう状態なのか、よくわからなかった。
彼方で声だけが聞こえくるような気がした。あとは身体が冷えていて寒さだけが伝わっていた。
-おはよう-
「おはよう?」
-そういえば、自分は??確か回収に向う艇を待っていて・・・なぜここに、いるのだろう?ここは少なくとも、味方の側ではないような予感がしていた-
・・・死んだのかな?確か直前に何か大きな機械がやってきていたし・・・
「おめでとう。君は祝福された。気分はどうだい?」
子供の声だとわかった。しかも4−5歳位のまだ幼児を出たばかりのような独特のくぐもった声。
誰だろう?ここは・・・御使い達に捕まったのだろうか?
幼児が自分を見下ろしていた。きょとんとした表情なのに、言葉はしっかりしていたのが奇妙で病みががりの身には応えた。
くぐもった声がかすんだ目の先の像から呼びかけてくる。
「だんだん意識が回復してくると思うよ・・・何から話そうかい?」
「ボクは君達巨人達の言う「敵対存在」その御使い達の長、「留守を護る者」だよ。今回は災難だったね。あの巨人達に見捨てられたんだね可哀想そうにいに・・でももう大丈夫、だよ。
「「君達」」 はこれから新しい生を生きる権利が与えられたんだ!祝福するよ。お誕生日おめでとう!」
・・・君達??・・・・
その声の主の言う意味がわからなかった。かろうじて首を動かすことが出来た。
辺りには一面に星の光が投射されていた。
プラネタリウムのように奇妙に現実感のない風景だった。その遠い先に川の流れるような微かな音がした。本当にそのような光景が広がっているのかもしれないと思ったがまだ目が焦点をきちんと結ぶ事が出来なかった。
「ここは、君達の心象風景を映し出す回廊。御使い達が試練の場と呼ぶ場所さ・・・」
トゥールは先ほどの問い「君達」の意味を尋ねようとしたが言葉を発する直前、自分の中の何者かがそれをさえぎって声を発しているのに気づいて驚いた。そしてその声の音色にも!
「君達??どういうことなの?今ここのいるのは誰なの?これは誰?私は今どうなっているの?」
それはヘカリィの意識のようだった。けどもその声色はまぎれもなく。
上から聞こえる声、御使い達の長を名乗る者の声が返事を返した。
「本当は少しづつ慣らしていこうと思ったんだけどね・・・・まず、この姿は鏡に映してみればわかるだろうね。ボクの話が終わる頃には
その機会を考えてるよ」
「君達2人に謝っておかないとね。まずその入れ物、はっきりいうと、君達の意識はあの巨人の御使いが乗り換えた抜け殻の中にある。マールといいう名前で呼んでいたね、君達は・・・・」
「2人」は早く確かめたいと思った。何が起きているのかを。それと同時にお互いの意識が一致し始めているのに戸惑いを隠せなかった。
「そろそろ意識の融合が始まったようだね。うん、事情を説明しないといけないね。まず、ヘカリイ、君の身体はマールが奪っていった。だから、君の意識は宙に浮いたまま、あの交換房の中をさまよっていたんだ。」
「そしてトゥール君、君の待ち合わせ場所にあの巨人の御使いは来なかった。たぶんはじめから置いていくつもりだったのかもしれない。ボクの言うことを信じ
るかどうかはわかんないけど、疑問に持つなら、今後君達がボクタチの条件、試練を受けて御使いとして生きていくのなら、自力で確かめるのは止めないけど
ね」
・・・どうなった??・・・
「ボクの仔達、下級御使い達が手荒なことをしたね。抵抗したので機械で押しつぶそうとしていた。普段、再生の機会ある物はあちらの者でも一度ボクに相談してよっていってんだけど、下まで伝わらなかったようだね。かなり傷んでいたのでこういう方法を取ることにしたんだ」
それはあの巨人達の御使いが捨てていった抜け殻だったのだけど、君達には良い助けとなった。
かなり調整したから、不具合はないと思うよ!」
「彼らは」唐突な自体にその生き物の説明をただ受け入れて聴くより他にはなかった。
・・・一体何のために??・・・
その生き物はこっくりとうなづいたように見えた。
「理由かい?君達の意識を探った時、ここの御使い達と一緒に試練を経たら、もしかして後継者の1人を継いでくれるかもしれないと思ってね」
・・・後継者・・・・
「そう、ボクはずっとここにいるわけにはいかないんだ。仲間達との取り決めでね、いづれ他の世界を治めないといけなくなる。ここの御使い達の生きる理由の1つはそこにもあるのさ。大分意識が協調してきたみたいだね。相性はよいみたいだね。」
「これからは1つの人格として生きていくことになる。名前を考えておくよ。それからボクは御使い達にミタンニって呼ばれている。意味は何も知らない子供ってことだね。謙遜じゃなくてこれがボクの尊称なんだ。その意味もいづれわかる」
・・・これからどうやって・・・・
「君が再生して落ち着くまでに指導係がいるね。あとで紅の御使いをよこそう。それまでしばらく療養しているといいね。あ、そうそう。君達。いや、君の呼び名の候補を後で紅から渡してもらう。その中からすきなのを選ぶといいよ。じゃあ、またね!」
そうしてその生き物は去っていった。
身体の自由が効くようになると彼らはそこに鏡を見た。自分の意識が他人の身体にあること、それが現実のものとなっておそってきた。そ鏡に映るマールの裸体を確かめると同時に入りまじった不安と錯綜、苦痛がねじれたように彼らを襲ってきて、再び倒れてしまった。
意識が遠のく直前に遠くで川の流れるような音がしていた。
自分はこれからここで生きていくのかと思うと、まずそれまでの張り詰めた気持ちが解けていくのが先で、その後のことは全てが早口の夢心地のようでなにもつかめなかった。
時折自分のものでないような感触がお互いを縛り合い、その度に軽い頭痛のようなめまい、互いを認めようとすると怯えのようなものが自分達の中を行き来するのが分かった。
紅が現れたのはそれから1周期ほど過ぎた後になった。
4 午後という名の記憶
彼の家は川岸の土手から少し離れた所にあった。
とうもろこし草が黄色い綿毛を飛ばし始めているこの季節が過ぎると「込め」の収穫をしないといけない。比較的南にあるここルワ−スでも真冬になるとちょっと涼しくなる。
黄緑と黄色が級友たちが彼を思い出す時に感じたイメ−ジだった。もちろん私達の中にもそれは頭の中にあったに違いない。だから彼の名はとうもろこし草畑の色とのイメ−ジと生まれた日の丁度一年前に祖母をお迎えに来た浮き舟の名をとってニ−ナ・ウィナスという。
もちろん彼はそんなことは全く気にしていない。こうして彼の資質は整い、私たちは彼を祝福する。
私の相方、彼女は川に落ちてお迎えを受けることなくはかなくなってしまった。それは大変恥ずべきことだ。だが私は彼、そして一族の皆にショックを与えたくなかった。幸い魂は間に合い、私は使徒庁に彼女の復活を頼んだ。ある試練と引き換えに。
彼女があることを実行するために彼を呼んだその日、幾分日差しを増した太陽は小屋の片隅をかすめとっていった。
マールがここに来て2年余り、細心の注意をこらして周囲に溶け込み、すべての出来事を当たり前のように受け止めて生活をしたつもりでいた。
それでも、わからないことがあった。
それを無理にこじ開けようとすると、この脆い世界が壊れそうな気がして、同時に彼女の立場も崩壊するような気がして、これまで実行できなかった。
「お迎えの祭りに出るなら、おうちの人達にもきちんと話をしないとね」
彼女は仔に念押しをした。
「うん、まえから少しだけそういう話をしてるよ。こんどはちゃんと話してわかってもらうんだ」
「お迎えに呼ばれるのは、14を過ぎたもの、そして・・・・」
「とくべつにお迎えをねがって、ゆるされたひと、だよね。どきどきする」
「恐くないの?もしかしたら帰ってこれないかもしれないじゃない」
マールは本人の意思で決めたことを確認するかののように言った。
「ううん、願ってお迎えを受けた人は、御使いさまになれるんだって」
はじめて聴くことだった。興味を持ちながら悟られまいとお茶を口にする自分自身がこっけいだった。
こんな「仔」相手に。
「それは本当なの?」
「うん、おかあさんと、おとおさんが前に小声で言ってた。ぼくがそういう人はどうなるのってきいたらね」
「いつなの?」
「ずっと前、おまつりのときに聴いたの」
今頃になって仔の口からこんな重要なことが聞けるとは思わなかったので、マールはたじろいだ。
「そういう人を噂でも聞いたことある?」
「ううん?ないよ。たぶんそうだしてもね、わかんないんだって、あ、これもらっていい?」
マールは菓子に手をつけずにいたのに気づいた。彼が両親からもらってきたものらしい。
かつての世界で例えるなら「クッキー」という焼菓子に似ていた。
昔なにかの映画で見たようデジャヴュ、自分がその登場人物のような気がしていた。
−こんなとき気の利いた曲でも掛けるとよいのだけど−
小屋には小型の音楽セットがある。それにの選曲センサー触れて望む曲をリクエストした。
ただその内容に、り地球にいたときのような刺激のあるリズムやメロディなど期待できなかったが。
なにしろここには流行歌もジャズもロックも、いやポピュラー音楽になたるようなものがまるで見当たらないのだから。
音楽という娯楽について言えば、最初マールはここはかつての旧時代にあったという修道院や、訓練所の中のような息苦しさを感じていた。
あるのは自然を描写したメロディ、器楽曲、それも大編成の交響詩などではなく、まるで中世の吟遊詩人のようなシンプルな曲、そして少年少女の声楽による童謡や歌曲、いやこれは成人がいない世界だから無理もないが。
そこまで頭の中でめまぐるしく思いを引き出して、なぜこの道に進む前に音楽の道をもう一度考えなおさなかったのだろうと少しだけ後悔していた。
もしその方面で推薦される程の実力を蓄え、何かの機会にあのとき遠い他所にでも行ってしまっていればあるいは。
でもそれももう終わってしまったこと。回想の中に生きるにはまだはやすぎた。
「ねえ、マールさん、さっきからぼうっとしているよう!」
「少し考えごとをしていたの。ねえ、さっきそんな人いてもわかんないんだって言ってたわね。どういうこと?」
「姿形が変ってしまうんだって。御使いさまになると、とてもぼくたちとは違うとってもすごい人になるから、なんだって」
マールは続きを訊ねるのをやめた。この仔なりに理解した範囲を超えた質問をしてもしかたがない。
流れている曲、いや調べとでもいうべきものは聞いていると清水に手を触れたかのような不思議な気持ちがした。
そのようなものをマール自身が求めているのかもしれなかった。この器械は人の感情を鏡のように映してそれに応える調べを返すという。
「御両親ともよく話をして、キミの気持ちが固まったら、私から渡すものがあるの。そのときが来たらまた話しましょうね」
マールは彼を送っていくことにした。
空は少し夕が迫っていて、スクーターの揺れる周期に併せて小さな寝息が聞こえているのに気づいたのは、遠くに明かりと広葉樹の下に建っている家屋が見えるか見えないかの時間が過ぎた後だった。
風は少冷たく袖を濡らし、一番星が丁度その樹木を超したばかりのあたりでゆらめいていた。
5 それぞれの夜
1
近くまで送ってもらっているうちにすっかり日はおちて、白い月の上を青い月が遠慮がちに通りすぎる刻になった。
走ればすぐそこまでのところまできたのに・・・
「マールさんは?一緒に夕食過ごしていくよ!」
「私はここで。明日の準備をしないと」
彼はそこで少し名残惜しそうにしていたが、向きを変えて、走りはじめ、そしてすぐ歩み足になった。
「ただいま」
暗闇の中で、急に見えた光で少し目を細めてた。
-今日は、話さないといけないことがあるんだ-
でも、どうやって口にしてよいかわからなかった。
その答えを知りたくて残っていて、いつもよりも遅くなった気がした。
ただいま。と声を掛けた。いつものように。
「おかえり。今日はずいぶん掛かってたの?」
「うん」
お母さんは夕食を出してきた。僕はマールさんとこで少し頂いたので、そのことを話そうかと思っってやっぱり話せなかった。
「噛むもの」をもらった後、
2
仔が手紙を書いていた頃、そこから思いもつかない場所に彼の話題の中心がいた。
窓の隙間から夜風が漏れて薄いレ−スのカ−テンをもて遊び、二つの月に照らされた様々な影法師の双子たちがちらちらと戯れあっていた。
ここまでは全て順調だ。もしこのままの時が続くならば彼女はこの強運に感謝もするだろう。ただしそれはこの星を見守っている神々ではなく、彼女自身の信ずる運命の力にである。
同じころ、 マ−ルも日記を書いていた。しかしこれを保存するつもりはない。書くことで入力すべきなのは記憶だと思っているから。
なぜこんなことをするのかは考えないことにしている。ただ心配なのは、これまでに完全な成功例がないことだけだった。
−持ち帰れるかしら?−
前回の作戦は成功とは言えなかった。ただ、彼女自身がここに無事でいる、ただそれだけが評価出来る全てだった。
−今度こそは−
しかしその先に何が見えるのか、それを知るものはいない。
3
僕が砂のある場所から戻ってきてからそんなにたってないと思ってたのに、あっという間にお祭りの日がやって来た。
お祭りの日だからって大きなことがあるわけじゃない、だってこれは僕たちだけのお祭りだから、みんなで小さくだけど、楽しくやるんだ。それがこの日だって、一日がちょっとだけ長い日。月が一つに見える日。
「何をするのか、もう決めたのかい?」
銀黒のおじいさあんに聞かれて僕は困ってしまった。何になるんだろう?僕にはよくわからない。でも何をするかはもう決めている。
それはマ−ルさんと同じように“死ぬこと”だ。特別な場合に赦される老化剤を使えばお迎えが来る事は知っていた。もちろん猛反対された。御使い様の処でお勤めしている父さんが僕の側にまわってくれなかったらだめだったかもしれない。
あの人は言ってた。
−他の生き物はあんなに衰えて死んでしまうのにどうして人間だけにお迎えが来るのかって、考えたことある?−
−でも声がおかしくなったり、病気になったりするよ−
−それはどうかしら?−
僕は怖くはない。なぜならもしかしたらあの話が本当かもしれないって気がしてきたから。渡された香水の瓶に入った液体は二人だけの秘密。なぜこんなもの
を持っているのかという疑問はこの誘惑には打ち勝てそうにない。死の先には何があるのだろう、そして僕らは無事再会出来るだろうか?」
「『一緒に死ぬ』ではなく『天に召される』なら未だ安心できる。マ−ルさんには悪いけれど僕はその時そう思った。とても大変なことをしているというのにこ
んなことにむきになるなんて。友人も兄弟も何も言わない、言ってくれない。僕は特別なものになってしまったらしい。本当なら今頃普通に暮らしていけたの
に。 でも僕はそんな生活にはなじめそうにないだろうと、だからこんなことになったんだろうと、そうぼんやり考えている。
きっとお迎えのその日まで続くだろう。
九月の川、その初旬、岸辺からの放物線の先に波紋が生まれた。「一つぅ」 次に彼は黒曜石を思わせる手のひらの円盤状の固体を水面に滑らせた。それはす
ぐさまゆるい弧の先から勢いをつけていく。 輝きがすっとため息の空白を作るが、水面の鏡はすぐにその隙間に寄り添う。 今度は、跳ねた。「スキップ、ス
キップ」 こうしていると心のどこかに引っかかっているものが浮き上がってくるような気がして、彼は自分がなぜ知ってみたいと思ってたのかを、その原因を
みつけられるかを捜そうとした。「なぜ他の人に話したらいけないんだろう」「マ−ルさんが困るから?何故困るの?それを知ることがいけないことだから?」
それでも彼は直感的に、なにか悲しいことになる、そんな予感がしたのでそこで考えを止めた。−何があるのかを知ってその時、僕がどうしたらいいのかわか
るのかもしれない。だから今はマ−ルさんがそう言うのならそれでもいい− 決心はついた。円盤小石は手の平に帰ってきた。だがとても言い出せそうにない。
だとすれば・・・
それから四日後、彼の特別の赤い帯のついた手紙に対しての返事、緑のリボンのチュ−ブが配達されるのを見たものが誰かいたらしいそれはルワ−ス中で話題になった。「なぜなのかしら?まだあんなに若いのに」と向かいの坂の十〇になる運転手
「どうしてせっかくの人生を終えようとするんだろう。」それは彼に退屈な呪文と言わしめたあの学校の、彼のとなりのクラスの九つの先生。
「彼はそう決めたんだ。お迎えに価値を見出したのなら止めるべきではない。いやむしろルワ−ス中の誇りにしてもいいのでは。」
そう括ったのはとなりの町から交換品を運んできた来年十四になる老人。
だから彼が家の中に入ったその時からまる二日もの間沈黙が支配した。もちろん彼はその間ずっとあの川に近いとうもろこし草のある彼の家にいた。 その日の昼、彼の母が初めて口を開いた。
「どうしていってしまうの?」
「母さん、いつかお迎えの先には試練があるんだっていったよね。うまく言えないけど・・・きっとそれで終わりにならない、そんな気がする。僕は天の向こうで、母さんも、皆もきっと見守っていけそうな気がするんだ。」
彼にもし巨人達の概念が使えたならは探求心と共にそこで「ちから」か「勇気」という名に裏づけられた情動、その禁じられた「自信」を表現したのかもしれない。
しかしそこまでは彼もまだ気づいてなかった。一方彼女は彼のその言動に祝福すべき、誇るべきことなのだということを言い聞かせながらも、例えようもない空白を感じていた。しかしかろうじて彼女の十二年の経験がそれを判断させた。
「わたしは、まだ先でもいいと思うの。考え直して」
「お迎え」そのことには誰も口を出せないはずの彼の世界で、にもかかわらず彼女が引き止めを意図したことはいかにこれが巨人的な概念で控えめな表現だとしても彼にとっては最大の否定となった。